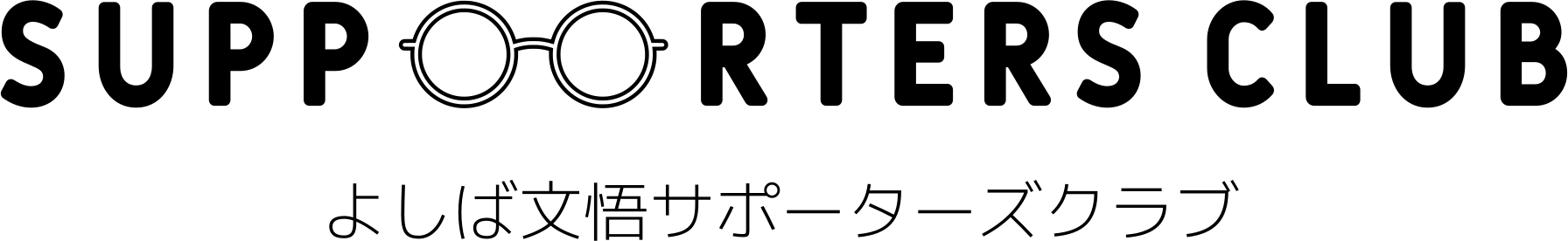2024/12/23に令和6年12月第4回小松市議会定例会を終えました。
今回もAIであるChatGPTの力を借り、要点をまとめ議会の振り返りを行います。
「プロンプト」と呼ばれるChatGPTに対して与えられる指示文や質問文を以下のように入力。
プロンプト:
https://smart.discussvision.net/smart/tenant/komatsu/WebView/rd/speech.html?council_id=60&schedule_id=2&playlist_id=5&speaker_id=36&target_year=2024
「議事録内容をわかりやすく要約して」
AIによる議事録回答整理
-
能登半島地震被災者への支援状況
質問:
- 地震で被災し、小松市に避難して生活している方々の人数や生活状況をどう把握しているか。
- 心の傷を抱えている方への支援や居場所づくり、特に冬季の移動サポートの必要性をどのように考えているか。
回答(副市長):
-
避難者数の把握
- 登録情報をもとに、小松市内では現在103世帯254人を支援。
-
支援体制
- 小松市社会福祉協議会内に「地域支え合いセンター小松」を設置。
- 被災者の状況に合わせ、訪問相談、物資支援、移動サポートなどを実施。
- 独居高齢者には見守りシステムや緊急通報装置設置等の支援も計上。
-
コミュニティづくり
- 第一コミュニティセンターでのミニコンサートやコミュニティカフェ、ボランティア団体による交流会などを開催し、被災者同士のつながりを支援。
-
子どもの心のケア
- 小中学校で必要に応じスクールカウンセラーが対応。
- アニバーサリー反応(発災の時期に再び心身の不調が出ること)などに注意している。
-
地域公共交通の再設計(小松のモビリティサービス)
質問:
- 金沢市でのバス路線廃止や縮小の動きなど、運転士不足が深刻化する中、小松市ではどのように地域公共交通を守り・再設計していくのか。
回答(市長):
-
現状のバス路線
- 小松市では北鉄加賀バス、北鉄白山バスが運行しているが、現時点で大幅な減便の予定はない。
- しかし将来的には運転士不足などの影響も懸念される。
-
再編に向けた取組
- 自動運転バス・公共ライドシェアなど、新たな交通モードの導入に積極的。
- 国交省の委員も務める名古屋大学の加藤教授を講師に「地域公共交通セミナー」を開催。
- 来年度は住民アンケートや交通ニーズ調査を進め、「こまつ地域交通プラン」を見直す方針。
-
今後の方向性
- バス・タクシー・鉄道だけでなく、自動運転やデマンド交通、地域乗合ワゴンなど多様な交通手段を組み合わせて「行きたいときに行きたい場所へ行ける」社会を目指す。
- 公共交通を福祉・医療・教育等と同様に、行政がイニシアチブを取って推進していく。
-
ドローン活用によるスマート物流
質問:
- スマート物流の実証で複数のドローンを遠隔操作しコストを下げる可能性があるが、これまでの成果・課題は何か。
回答(市長):
-
事業概要
- 令和5年8月に買物代行やフードデリバリー、共同配送を開始。
- クスリのアオキなど地元店舗や飲食チェーンとも提携。
- 令和5年8月~令和5年10月末時点で、買物&フードサービスは378件、共同配送2,035件。
-
ドローン配送の実情
- 天候や着陸場所での受け取り手配など、条件が厳しいため「実際にドローンで飛ばす回数」は伸び悩み。
- 現在は宅配の陸送がメイン。
-
今後の課題・展望
- 利用ニーズのある世帯を特定し、ドローン利用を定期化して省人化を図る。
- 公民館などをドローン着陸地点として活用。
- 平常時と災害時を区別しない“フェーズフリー”のデジタルライフライン構築を目指す。
- 技術の進展や規制緩和が進めばビジネスモデルとして確立していく見通し。
-
スタートアップ支援(イノベーションを促進する次のステップ)
質問:
- 「イノベーターズ・ミートアップ小松」の成功を受け、次はスタートアップ企業の創業や起業家をどう後押しするか。
- 小松駅東地区複合ビルの開業に向け、起業家を受け入れる環境づくりが重要ではないか。
回答(市長):
-
起業家育成の取組
- 現役起業家を講師に「こまつスタートアップラボ」を実施。既に市内で法人登記した受講者もいる。
- ビジネス創造プラザ内にインキュベーションルームを設置(現在は公立小松大学に貸与中)。
- 将来は市の遊休施設を活用するなど、企業支援の場を広げていく。
-
複合ビルとの連携
- 複合ビルや公立小松大学、コワーキングスペースなどが連携して新しいチャレンジを支援していく。
- 将来的にユニコーン企業の創出にも期待。
-
CDO(最高デジタル責任者)の必要性
質問:
- デジタル化を庁内横断で推進できる専門ポジション「CDO」の設置は考えられないか。加賀市などの事例も参考に、早期導入が望まれるのでは。
回答(市長):
-
小松市の現状
- 市はまだCDOを設置していないが、スマートシティ推進課が中心になり、住民情報システムの標準化や窓口改革、AI・RPA導入などを進めている。
- 被災者支援システムなども取り入れており、一定の成果を上げている。
-
CDO設置の考え
- 今後の検討課題として捉えており、現時点ではまず自治体DXを着実に進めることを優先している。
-
デジタル産業の発展、人材育成、ベンダー選定、およびデジタル化推進ビジョン
質問:
- ガバメントクラウドへの移行作業が全国的に遅れ、ベンダー不足が課題。地元IT企業の育成やデジタル産業の構造をどう考えているか。
- 小松市としてのデジタル化におけるロードマップやビジョンはどうなっているのか。
回答(市長):
-
ベンダー選定・デジタル関連経費について
- 小松市のデジタル関連施策(情報システムの構築・改修・保守など)にかかる費用は、大半を市外のベンダーに委託している現状。
- 令和5年度、スマートシティ推進課で執行している主要な事業費の決算額は約3億円。このうち、市外ベンダーに発注されたデジタル関連経費は約2億7,000万円。
- 自動運転バスや公共ライドシェア、GIGAスクールなど、デジタル技術を活用した事業でも、専門知識・実績を持つ市外ベンダーに依存するケースが多い。
-
地元IT産業・人材育成について
- 公立小松大学の生産システム科学科では、機械工学・情報工学・電気電子工学を組み合わせられる人材を育成。
- 市独自に行う「DX伴走支援モデル事業」では、企業のDX推進をサポートする費用の一部を補助し、伴走支援を実施。
- 企業立地支援制度の対象業種にも情報通信業を組み入れ、デジタル関連企業が小松市に進出しやすい環境づくりに取り組む。
-
小松市のデジタル化推進ビジョン
- 国の自治体DX推進計画の重点項目(システム標準化、窓口業務の効率化、AI・RPA活用等)に沿って進めている。
- 2040年ビジョンでは、最先端デジタル技術を活用したスマートシティを掲げており、総合戦略とあわせて独自のデジタル化ビジョン策定を検討。
- 今後も時代の流れを踏まえ、効果的にデジタル技術を活用していく。
まとめ
まず、能登半島地震被災者への支援状況についての質問は、実際にご意見をお聞きした上でまとめました。
震災から1年がたちますが、被災されて移住された方、仮設住宅で生活されている方、そのような方々への支援についての質問でした。
第一コミュニティセンターでの支援はとても喜ばれているとのことでしたが、そこに行けない人、精神的に参ってしまっている人へのサポートについてなど、回答をもらえたことには、質問した買いがあったと感じています。
もう一つのスタートアップなどに関しては、単純に「今のままでは進め方が多方面で間に合わないのでは」という思いから質問にしました。
小松市でやられていることは、全国の自治体で当たり前にやられていることでもあり、先進的というには少々弱いです。
独自性が難しいなら、デジタル化に関しては先手を打って整えるべきだと、環境がそろっていれば後で事を起こすときに話が早くなる、そんな視点が欲しいと感じています。
震災から1年がたちますが、被災されて移住された方、仮設住宅で生活されている方、そのような方々への支援についての質問でした。
第一コミュニティセンターでの支援はとても喜ばれているとのことでしたが、そこに行けない人、精神的に参ってしまっている人へのサポートについてなど、回答をもらえたことには、質問した買いがあったと感じています。
もう一つのスタートアップなどに関しては、単純に「今のままでは進め方が多方面で間に合わないのでは」という思いから質問にしました。
小松市でやられていることは、全国の自治体で当たり前にやられていることでもあり、先進的というには少々弱いです。
独自性が難しいなら、デジタル化に関しては先手を打って整えるべきだと、環境がそろっていれば後で事を起こすときに話が早くなる、そんな視点が欲しいと感じています。